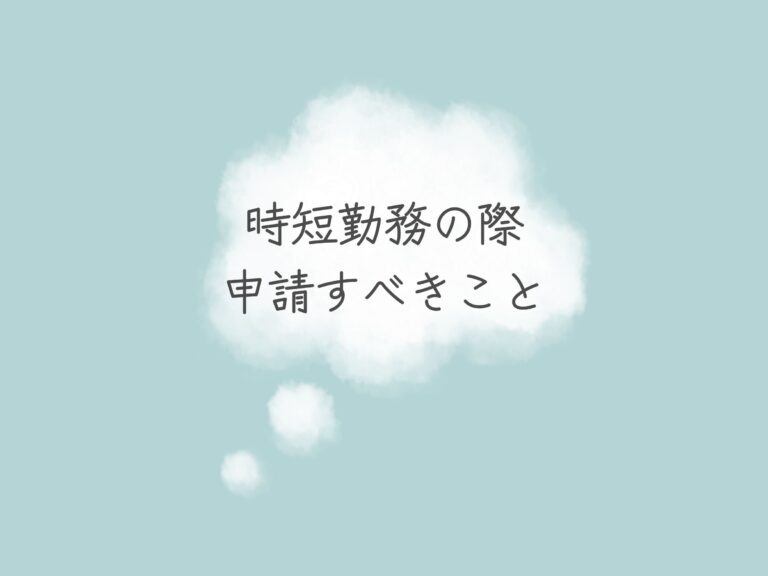時短勤務にすると給料が下がって、経済的に不安を感じてしまいますよね。
私自身も育休終了後、時短勤務で復帰予定なのですが、見込残業代制度でもある為、給料が11万円以上減ることが分かっており、少しでも手取りを減らさないようにする方法を考えました。
そこで本日は復帰後、時短勤務にする際に「申請しておくべきこと」についてお話いたします。
これから復職予定の方はぜひ参考にしていただければと思います。
復帰の際にやる事3選
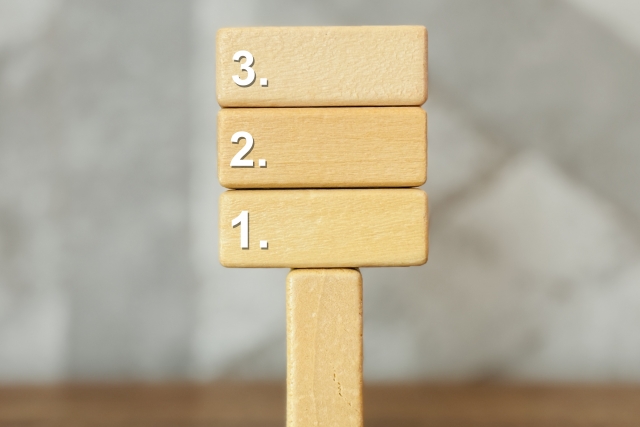
月末復帰を避ける
月途中で復帰をすると社会保険料の面で損してしまう事があります。
例えば・・・
- 3月30日が育休終了日で3月31日復帰にすると3月の1カ月分の社会保険料がかかる
- 3月30日が育休終了日で4月1日復帰にすると3月の1カ月分の社会保険料が免除
上記のように月の最終日に在籍してることによりその月の1カ月分、丸々社会保険料がかかってしまうのでできれば避けるのがおすすめです。
基本的に育児休業は子の誕生日の前日までと法律で決まっていますが、職場への復帰日は会社と相談して決める事が可能です。
つまり、育児休業終了日~復帰日の間は一般的な「休業扱い」になります。
なので私も月の末頃が育休終了日ですが、会社に交渉して1日復帰にする予定です☆
社会保険料軽減
基本的に時短勤務にしても、社会保険料に関しては従来(育休前)の給料額で算出された金額が徴収されます。
算定基準としては毎年4月~6月の標準月額報酬で算出されてその年の9月~翌年の8月までの1年間は同金額となっています。
時短勤務でただでさえ手取りが減るのに社会保険料は従来通り天引きがあってで更に手元に残るお金が減ったら生活に不安を感じますよね。
なのでこの状況を減らす措置として以下の手続きを人事労務担当者に依頼しておきます。
- 社会保険料の減額:育児休業終了時月額変更届の提出
- 年金受給額の維持:厚生年金保険養育期間標準月額特例申出書の提出
1.社会保険料の減額:育児休業終了時月額変更届の提出
時短勤務開始から3カ月の標準報酬月額を基準とした社会保険料に変更が可能になります。
つまり、新保険料の適用は4カ月目からとなるので復帰後3カ月までは従来の金額で支払う必要があるものの、最短で時短勤務時の報酬月額で社会保険料の見直しがされます。
2.年金受給額の維持:厚生年金保険養育期間標準月額特例申出書の提出
こちらは時短勤務により標準報酬月額が下がった場合でも将来の年金額を維持するための手続きになります。
つまり、時短勤務で給料が下がっても従前の標準報酬(育休前)月額と同等の収入を得たとみなして年金額が計算されるので老後に有利となります。
どちらも申請するだけで今も将来も手取り金額が増えるので私自身もすぐに会社に依頼する予定です☆
育児時短勤就業給付
2025年4月~開始予定の制度で申請は事業主なので、復帰の際に人事労務担当者に相談します。
制度内容としては2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金の10%が支給されるようです。(時短の幅が短い場合は賃金と給付額の合計が時短前賃金を超えないように調整されます)
給付を受けるには多少の条件はあるものの、正社員として時短勤務(6時間以上)であればほとんどの人が該当するようなので私も復帰後すぐに会社に申し出る予定です。
詳しくは厚生労働省のページで確認できます…!
どれくらい効果がある?

上述で紹介した制度を全て利用した場合、どれくらい違うのか私の状況を例に算出してみました。
私の場合、産休前の標準月額報酬は410,000円、時短時の標準月額報酬は240,000円です。
| ①月末を避ける | 20,459円 |
| ②社会保険料軽減(保険料) | 67,864円 |
| ③社会保険料軽減(厚生年金) | 算出不可 |
| ④育児時短勤就業給付 | 276,000円(概算) |
| 合計 | 約364,323円 |
①育休前の標準月額報酬で算出しました。
②10月復帰予定なので、(10月~8月の育休前等級(11カ月))ー(3カ月分は育休前の等級+8カ月分は育休後(時短)の等級)で算出しました。
③厚生年金は受給開始年齢や寿命等の予測ができず、算出不可能でした。
④時短勤務給料額(概算)の10%×12カ月(育休1年で復帰後、子の2歳の誕生日前日まで)
上記の申請だけで合計36万円ほど変わることが分かりました…!
最後に

本日は復帰後、時短で勤務する際に申請すべきことについてお話させていただきました。
世の中には知らないと損する事がたくさんあり、どれも申し出ないと適用されません。
私自身も得する情報を全て把握はできていないと思いますが、価値のある情報は今後もこちらのブログで共有したいと思っていますのでチェックしていただければ嬉しいです。
是非、今できる事をやって上手にお金を貯めていきましょう☆
この他にも節約術や資産形成についての記事を公開していますので合わせて参考にしていただければと思います。
本日もご覧いただきありがとうございました。